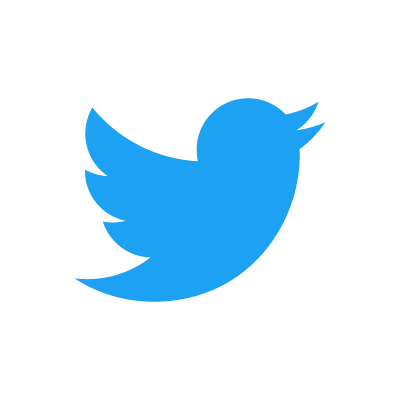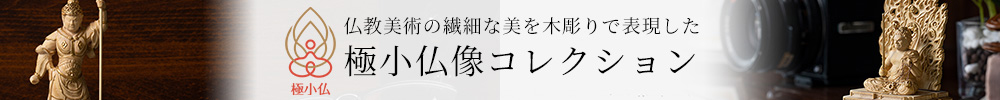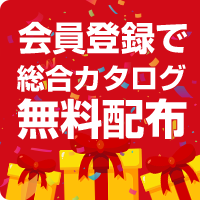- HOME
- 宮澤やすみの仏像ブツブツ
- 第250回 聖徳太子さんぽ2 三宿神社の毘沙門天
第250回 聖徳太子さんぽ2 三宿神社の毘沙門天
”神社に仏像を祀るという、神仏習合ファンにはワクワクするかたちが、ここに……”
神仏研究家・音楽家の宮澤やすみが、仏像とその周辺をブツブツ語る連載エッセイ。
こんにちは。MV(ミュージック・ビデオ)の制作を続けていると、頭の中でいろんなアイデアが出て作業が止まらなくなっている宮澤やすみです。音楽の仕事が減ってるうちに映像作家になっているかもしれません(冗談です)。
さて、東京世田谷、三宿の緑道を歩いて、前回記事では太子堂をご紹介。今回はその近くの三宿神社にやってきました。
このあたりを通る国道256号線は、かつては大山詣での参詣人が歩いた参詣道でもあります。
信仰の歴史を感じる道です。
そこにある三宿神社ですが、写真をご覧ください。
石造りの「三宿神社」という社標の隣の、「毘沙門天」と記してあるんですよね。
わたくしの大好きな、神仏習合のニオイがプンプンします。

神社の社名の隣に「毘沙門天」が並ぶ
境内に入ると、都内とは思えない緑あふれる丘の上に社殿があります。
毘沙門天は、仏教の守護神であり、お寺で見られる尊格ですが、神社にあるとはどういうことでしょうか?

毘沙門天を祀る社殿の隣に稲荷神社が並ぶ
ちょっと調べてみると、三宿神社はかつて「三宿城」という中世の城砦の中核をなす「多聞寺」が原型だそうで、その本尊こそ毘沙門天なのでした。毘沙門天は多聞天の別名ですから同一神です。

見た目は完全に神社だが祀るのは仏教の毘沙門天
多聞寺は一時期途絶えていたそうですが、地元住人が三宿神社として再興したのが明治18年の事。ご祭神を毘沙門天としたのですがこれがまずかった。
ご存知の通り明治以降は神仏分離の世の中になってますから、「神社に仏像があるのはいかがなものか」と、東京府が受け入れなかったそうです。
その後曲折あって、祭神を稲荷神である倉稲魂命(うかのみたまのみこと)としたのですが、まあ結局、氏子の皆様にとっては「三宿の毘沙門さん」と呼ばれ、実際に毘沙門天を祀り続けているのでした。タテマエと本音でございます。
神社に仏像を祀るという、神仏習合ファンにはワクワクするかたちが、令和の現代、ここ世田谷にありました。
前回記事のとおり、すぐ近くの円泉寺には聖徳太子を祀っています。
聖徳太子と毘沙門天は、並んで信仰される深い結びつきがあります。
くわしくは奈良・信貴山朝護孫子寺の伝承を検索してください。
その二尊がここ世田谷の三宿に並び祀られているのですが、三宿神社と円泉寺は、かつて一体だったのでしょうか。
多くの場合、神社の境内や近隣に別当寺(神社を管理する寺)が存在するのが、江戸以前のかたちでした。
時代をみると、三宿神社の前身である多聞寺は文明年間(1469年-1486年)の頃に吉良氏が築いたもの
いっぽう、お寺のほう(円泉寺太子堂)は、文禄4年(1595年)になって、賢恵和尚(聖徳太子像を背負って奈良からやってきたという)の夢告によってできたとされます(太子堂の原型が南北朝ごろという説もあります)。

円泉寺の聖徳太子像
地理的にはほぼお隣さんともいえる寺と神社ですが、双方それぞれの伝承があるだけで、両寺社のむすびつきははっきりしません。
まあしかし、お城があるくらいの地域の要に、毘沙門天が祀られて、その隣に、奈良からやって来た和尚さんが聖徳太子を祀る(伝承)のは自然なことと思います。
どちらが先かはわかりませんが、おそらく一体として信仰を集めていたんじゃないでしょうか。

すぐ近くは人気の街・三軒茶屋(5月撮影)
いずれにしても中世の世田谷地域に、聖徳太子と毘沙門天の信仰が根付いたということがわかりました。
もし、今後さらにわかったことがあったら、またこの連載に書くことといたしましょう。
それでは聴いてください。
デヴィッド・シルヴィアンで「Krishna Blue」
(おしらせ)本コラム筆者・宮澤やすみ関連情報
1.
宮澤やすみ作・ザ・ブッツ「君はソウルメイト!百済観音」
宮澤やすみYoutubeチャンネル
https://www.youtube.com/c/YasumiMiyazawa/
2.
宮澤やすみソロアルバム発売中
『SHAMISEN DYSTOPIA シャミセン・ディストピア』
購入は「やすみ直販」で
http://yasumimiyazawa.com/direct.html
(ネット決済のほか、銀行振込、郵便振替も対応)
宮澤やすみ公式サイト:http://yasumimiyazawa.com
宮澤やすみツイッター:https://twitter.com/yasumi_m
神仏研究家・音楽家の宮澤やすみが、仏像とその周辺をブツブツ語る連載エッセイ。
こんにちは。MV(ミュージック・ビデオ)の制作を続けていると、頭の中でいろんなアイデアが出て作業が止まらなくなっている宮澤やすみです。音楽の仕事が減ってるうちに映像作家になっているかもしれません(冗談です)。
さて、東京世田谷、三宿の緑道を歩いて、前回記事では太子堂をご紹介。今回はその近くの三宿神社にやってきました。
このあたりを通る国道256号線は、かつては大山詣での参詣人が歩いた参詣道でもあります。
信仰の歴史を感じる道です。
そこにある三宿神社ですが、写真をご覧ください。
石造りの「三宿神社」という社標の隣の、「毘沙門天」と記してあるんですよね。
わたくしの大好きな、神仏習合のニオイがプンプンします。

神社の社名の隣に「毘沙門天」が並ぶ
境内に入ると、都内とは思えない緑あふれる丘の上に社殿があります。
毘沙門天は、仏教の守護神であり、お寺で見られる尊格ですが、神社にあるとはどういうことでしょうか?

毘沙門天を祀る社殿の隣に稲荷神社が並ぶ
ちょっと調べてみると、三宿神社はかつて「三宿城」という中世の城砦の中核をなす「多聞寺」が原型だそうで、その本尊こそ毘沙門天なのでした。毘沙門天は多聞天の別名ですから同一神です。

見た目は完全に神社だが祀るのは仏教の毘沙門天
多聞寺は一時期途絶えていたそうですが、地元住人が三宿神社として再興したのが明治18年の事。ご祭神を毘沙門天としたのですがこれがまずかった。
ご存知の通り明治以降は神仏分離の世の中になってますから、「神社に仏像があるのはいかがなものか」と、東京府が受け入れなかったそうです。
その後曲折あって、祭神を稲荷神である倉稲魂命(うかのみたまのみこと)としたのですが、まあ結局、氏子の皆様にとっては「三宿の毘沙門さん」と呼ばれ、実際に毘沙門天を祀り続けているのでした。タテマエと本音でございます。
神社に仏像を祀るという、神仏習合ファンにはワクワクするかたちが、令和の現代、ここ世田谷にありました。
前回記事のとおり、すぐ近くの円泉寺には聖徳太子を祀っています。
聖徳太子と毘沙門天は、並んで信仰される深い結びつきがあります。
くわしくは奈良・信貴山朝護孫子寺の伝承を検索してください。
その二尊がここ世田谷の三宿に並び祀られているのですが、三宿神社と円泉寺は、かつて一体だったのでしょうか。
多くの場合、神社の境内や近隣に別当寺(神社を管理する寺)が存在するのが、江戸以前のかたちでした。
時代をみると、三宿神社の前身である多聞寺は文明年間(1469年-1486年)の頃に吉良氏が築いたもの
いっぽう、お寺のほう(円泉寺太子堂)は、文禄4年(1595年)になって、賢恵和尚(聖徳太子像を背負って奈良からやってきたという)の夢告によってできたとされます(太子堂の原型が南北朝ごろという説もあります)。

円泉寺の聖徳太子像
地理的にはほぼお隣さんともいえる寺と神社ですが、双方それぞれの伝承があるだけで、両寺社のむすびつきははっきりしません。
まあしかし、お城があるくらいの地域の要に、毘沙門天が祀られて、その隣に、奈良からやって来た和尚さんが聖徳太子を祀る(伝承)のは自然なことと思います。
どちらが先かはわかりませんが、おそらく一体として信仰を集めていたんじゃないでしょうか。

すぐ近くは人気の街・三軒茶屋(5月撮影)
いずれにしても中世の世田谷地域に、聖徳太子と毘沙門天の信仰が根付いたということがわかりました。
もし、今後さらにわかったことがあったら、またこの連載に書くことといたしましょう。
それでは聴いてください。
デヴィッド・シルヴィアンで「Krishna Blue」
(おしらせ)本コラム筆者・宮澤やすみ関連情報
1.
宮澤やすみ作・ザ・ブッツ「君はソウルメイト!百済観音」
宮澤やすみYoutubeチャンネル
https://www.youtube.com/c/YasumiMiyazawa/
2.
宮澤やすみソロアルバム発売中
『SHAMISEN DYSTOPIA シャミセン・ディストピア』
購入は「やすみ直販」で
http://yasumimiyazawa.com/direct.html
(ネット決済のほか、銀行振込、郵便振替も対応)
宮澤やすみ公式サイト:http://yasumimiyazawa.com
宮澤やすみツイッター:https://twitter.com/yasumi_m