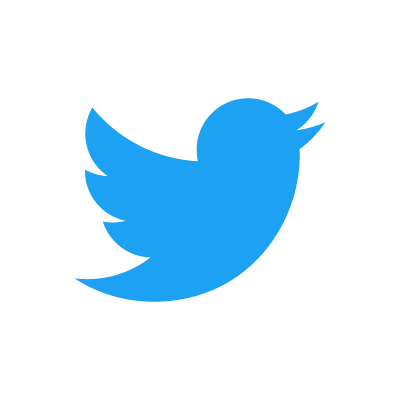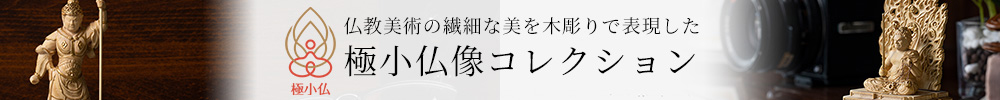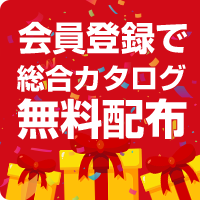- HOME
- 宮澤やすみの仏像ブツブツ
- 座っている観音、地蔵
座っている観音、地蔵
ここんとこずっと立ち姿の仏像の話で、まあ「立ち話」もなんですから、座ってブツブツいたしましょうよってことでしてね。
それにしても、こんな小文にも反響いただくようになりどうもありがとうございます。
もうホントただブツブツつぶやくだけの小連載でして、たいした結論は全然ないんですよね…しかし有難いことに連載なので、ちびちびとちょっとずつ、小出しにやっていってるという次第です。
で、座った像は、大仏さんみたいに主役としてお寺の真ん中にどーんとあるのがしっくりきます。つまりご本尊。
ご本尊は、本来なら如来さんが適任なんでしょうけど、時には菩薩が本尊になることもありますよね。
こちらの写真は、奈良の福智院をテレビのロケで訪れたときの写真です。

ロケするもオンエアではばっさりカット…(泣)
ご本尊は地蔵菩薩なんですけど、一般的なかわいらしいお地蔵さんとはちがって、貫禄たっぷりですね。
服装や体つきだけ見ると、「ほぼ如来」っていう感じです。
(ただし足の組み方がゆるんでいてそこだけ少し菩薩感を出してはいる)

差し入れは天平庵さんのどら焼き。隠れミッキー?じゃないですよ!洲浜型っていう
こうやって、貫禄たっぷりに造るのは、やっぱりご本尊として如来に匹敵する貫禄を表現してるみたいです。
こちらの写真は、先日の東京国立博物館で話題となった奈良・櫟野寺のご本尊。十一面観音菩薩。

報道内覧会にて。重量級の迫力でした
前々回で紹介した妖艶な十一面さんと、印象がぜんぜんちがいますよね。
坐り方は、結跏趺坐(けっかふざ)といって、仏像の座り方の基本です。悟りを開いて深い瞑想に入った状態とされます。
学芸員さんの解説によると、櫟野寺の像はやはり如来の風格を表現しているそうです(とくに腹部の二本の皺は天台系の薬師如来に見られる特徴だそうで)。
そんなわけで、菩薩なんだけどご本尊として祀るときにはそれなりの風格のある姿、つまり如来っぽく造るやり方もあるんですね。
(もちろんシュッとした立像の例もたくさんありますけどね)
あと、大宰府の観世音寺に行くと、収蔵庫に観音菩薩の坐像があります(写真は検索すれば出ます)。
今でこそ収蔵庫の角っこに座ってますが、もともとはお堂のご本尊としてセンターに座ってました(旧講堂本尊)。
このお方もやっぱり堂々とした体格をしています。
立っている、座っているという姿勢、いろんな意味が込められているんですよね。
このほかにも半跏坐とか輪王坐とか大和坐りとかいろいろあるけど、また機会あれば触れてみたいと思います。
それにしても、こんな小文にも反響いただくようになりどうもありがとうございます。
もうホントただブツブツつぶやくだけの小連載でして、たいした結論は全然ないんですよね…しかし有難いことに連載なので、ちびちびとちょっとずつ、小出しにやっていってるという次第です。
で、座った像は、大仏さんみたいに主役としてお寺の真ん中にどーんとあるのがしっくりきます。つまりご本尊。
ご本尊は、本来なら如来さんが適任なんでしょうけど、時には菩薩が本尊になることもありますよね。
こちらの写真は、奈良の福智院をテレビのロケで訪れたときの写真です。

ロケするもオンエアではばっさりカット…(泣)
ご本尊は地蔵菩薩なんですけど、一般的なかわいらしいお地蔵さんとはちがって、貫禄たっぷりですね。
服装や体つきだけ見ると、「ほぼ如来」っていう感じです。
(ただし足の組み方がゆるんでいてそこだけ少し菩薩感を出してはいる)

差し入れは天平庵さんのどら焼き。隠れミッキー?じゃないですよ!洲浜型っていう
こうやって、貫禄たっぷりに造るのは、やっぱりご本尊として如来に匹敵する貫禄を表現してるみたいです。
こちらの写真は、先日の東京国立博物館で話題となった奈良・櫟野寺のご本尊。十一面観音菩薩。

報道内覧会にて。重量級の迫力でした
前々回で紹介した妖艶な十一面さんと、印象がぜんぜんちがいますよね。
坐り方は、結跏趺坐(けっかふざ)といって、仏像の座り方の基本です。悟りを開いて深い瞑想に入った状態とされます。
学芸員さんの解説によると、櫟野寺の像はやはり如来の風格を表現しているそうです(とくに腹部の二本の皺は天台系の薬師如来に見られる特徴だそうで)。
そんなわけで、菩薩なんだけどご本尊として祀るときにはそれなりの風格のある姿、つまり如来っぽく造るやり方もあるんですね。
(もちろんシュッとした立像の例もたくさんありますけどね)
あと、大宰府の観世音寺に行くと、収蔵庫に観音菩薩の坐像があります(写真は検索すれば出ます)。
今でこそ収蔵庫の角っこに座ってますが、もともとはお堂のご本尊としてセンターに座ってました(旧講堂本尊)。
このお方もやっぱり堂々とした体格をしています。
立っている、座っているという姿勢、いろんな意味が込められているんですよね。
このほかにも半跏坐とか輪王坐とか大和坐りとかいろいろあるけど、また機会あれば触れてみたいと思います。